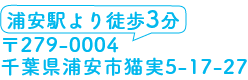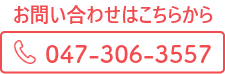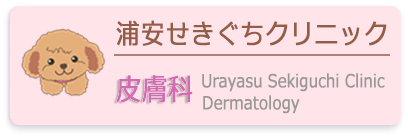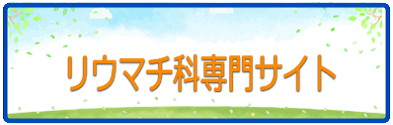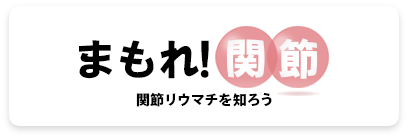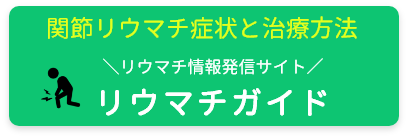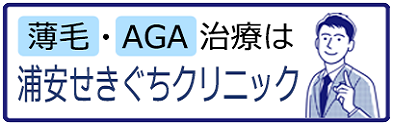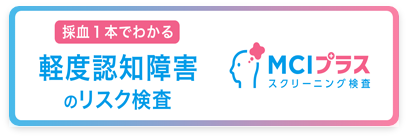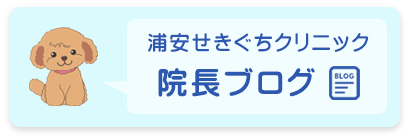ブログ


2021.12.13
内科
漢方薬の副作用と散歩の語源について|漢方|内科|浦安せきぐちクリニック
散歩の語源について、お話します。後漢から唐の時代の古代中国で、不老不死の効果や虚弱体質の改善に効果があるということで五石散(ごせきさん)という薬物が流行しました。その中身は、鍾乳石、硫黄、白石英、紫石英、赤石脂という5種類の鉱物でした。鉱物を飲まされていた?むしろ率先して服用していた?この五石散を服用すると体が温まる「散発」という現象が起きました。もし、散発が起こらず薬が内にこもると中毒を起こして死んでしまうとされたため散発を維持するために絶えず歩き回らなければならず、これを行散と言ったそうです。そのあり様から「散歩」という言葉がでてきたようです。これは激しい例ですが、漢方薬に副作用が少ないというのは間違いのため、勝手に何種類も漢方を服用することはお勧めしません。
文責:浦安せきぐちクリニック(内科・リウマチ内科・皮膚科・泌尿器科)院長 関口直哉